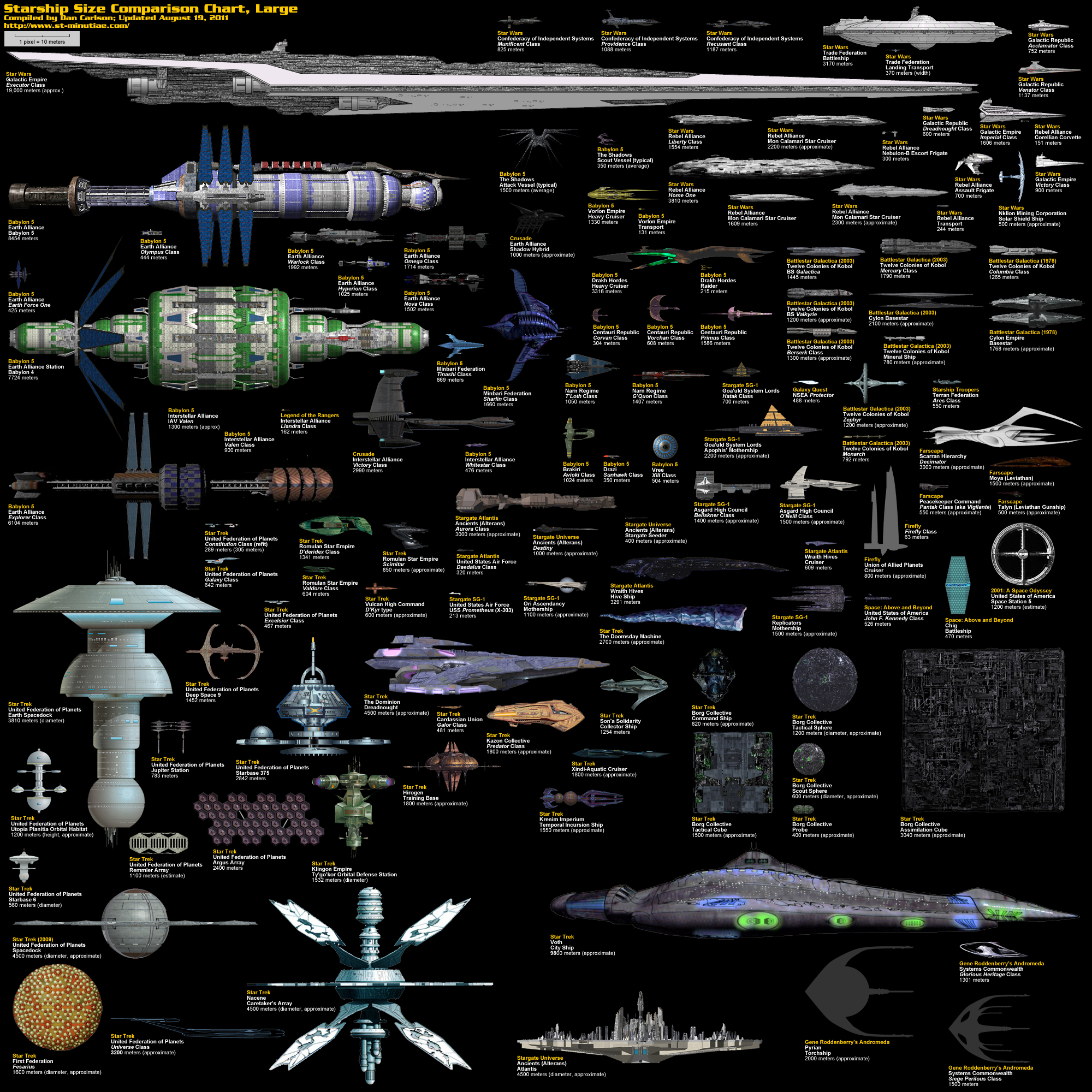さて、気を取り直して第四回目(いったん最終回にしますよ)の今回は、「価格」「保管・保存性」について、電子書籍と紙の本のそれぞれを考えてみよう。でも、価格については考えれば考えるほど、調べれば調べるほど難しい問題。僕みたいな立場の人間が簡単に語れるような問題ではないな。結論なんて出せるわけもないし。
だから、ここはさらっと書かせてもらっちゃう。
9.価格
《電子書籍》
・ある程度自由に価格設定できる
→特に自己出版の本は、下限と上限の範囲内で好きな価格にできる。(時に、信じられないような強気価格に出会ったりもする)
→配信元の判断で、キャンペーンやセールなど、価格をある程度柔軟に変更できる。
→原価と売価のバランスだけではなく、紙の本を保護したい度合いなども加味した価格設定をしているように思われる。あまり安く設定してしまうと、紙の本が売れなくなってしまうというバランスも?
・基本的には古本や再流通がないため、販売者の決めた価格で消費者の手に渡る。
→KDPでも作者の意向と関係のないキャンペーンによる安売りがあったりするけど、安売りしたくない(=作品の価値を安く見せたくない)作者にとってはマイナスにも……。
・基本的には紙の本より安い
→そうでないものもある。
→製造にかかるコストを考えると、遥かに安くできるのではないかと考えがち。でも配布の想定量が桁違いに少ないから、そこは単純に比べられない。
電車の中を見回した時、文庫本や新書、ハードカバーを読んでいる人は毎日必ず見掛けるけど、KindleやKOBOを持っている人はめったに見掛けない。タブレットで読んでいる人も見るけど、絶対数は少ないかな。
→洋書では圧倒的に安いケースが多い。でも、翻訳の文庫本より洋書の電子書籍の方が高い場合もある。
・数多くの無料本が存在する
→古くは青空文庫やプロジェクト・グーテンベルク。ネット上には著作権切れや作家が自主的に提供した書籍など、無償の本が大量に存在する。(WEB上の小説は別カテゴリーとして)
《紙本》
・書店での安売りは、基本的にない
→再販制度で守られ、新刊本が安売りされることは(今のところ)ない。
価格要因で売れ残った本を安く捌くことができないという弊害もある?
市場全体で見ると、返本するより売り切った方が良い場合もあるのではないか。
→「特価本市場」というものも存在するらしい。新古書として流れる「ゾッキ本」というやつ。
これは限りなく新刊に近い形のものが安売りされるが、あまり一般的とはいえないだろう。
・古本に関しては自由度が高い
→出版社にも著作権者にも1円も入らないから、「本の価格」とはまた別か。
しかし、電子書籍との比較で言えば、これは紙本の利点。
・図書館に配本されていれば無料で読める
→前回も書いたとおり。
いかがでしょう?
商業書籍における電子書籍の価格設定はまだ迷走しているようにも思えるし、だからこそ戦略的な値付けをした者がいきなり大ヒットを生み出すことがあったりする。逆に、紙の本と同じ価格の電子書籍でも、ちゃんと売れているケースもある。
要は、価格設定ではないんだな。電子で読みたい人はそっちで買うし、紙で読みたい人はそっちで買う。理由はそれぞれだし、電子書籍はかつて考えられたブレイクを迎えられないながらも、なんとか紙と共存している。という状況なのか。紙が、でなくて、電子が紙と。
電子書籍は安い。ってイメージがあるけど、それは一概には言えないと思う。個々の価格設定はケースバイケースだし、商業的に流通している本を、「所有欲を満たさなくて」いいなら、上述の図書館とか、紙の本の方がずっと多用な方法で読めるんだしね。(電子書籍を借りるってのもあるけど、読み終わらないうちにデータが消されちゃうこともある)
10.保管・保存性
《電子書籍》
・ひと昔前の神話として、電子書籍は永遠なんてのがあった
→冗談言っちゃいけない。電子データの永続性なんて、いまや誰も信じちゃいない。
コンピューターの世界では、たった20年前のデータでも全く読めないことが頻発するなんて常識だ。フォーマットの変化もあるし、OSの構造変化によって、データ自体を受け付けないことだってある。
汎用的なフォーマットだと信じられていたものでも、気が付くとどのソフトでも開けなくなっていた。なんてことも起こるしね。
・書棚データはクラウドにあるから、端末が壊れても買い替えても安心だ
→これも神話程度だ。一度購入した本でも、出版元の都合で読めなくなっちゃうこともある。だいたい、電子書籍のデータは購入者が所有権を持っていなかったりする。《読める権利を買う》ということらしい。
だから、そのデータの永続性なんて保証する必要もないらないし。
これはひどいな。
→プラットフォーム自体がなくなってしまう危険性も大きい。
つい最近も、一つ消えたし。
・もし、データが1文字でも壊れたら、その書籍データはおしまい
→そんなことがあり得るかどうか分からないけど、データってそういうもの。電子書籍端末を狙ったウィルスが作られれば、全ての本がダメになることもあるだろう。クラウドにまともなデータがあっても、DLした瞬間に読めなくなるウィルスとか、簡単に作れそうだ。(あ、もちろん僕にはそんな難しいことは出来ませんよ)
何しろ、タグが1文字壊れれば開けなくなっちゃうんだから。
・濡れてもいい端末もある
→KOBOにはお風呂で読める端末があるらしい。これはメリットか。
《紙本》
・ちょっとした不注意でページが破れてしまうことがある
→それでも、紙の本は読める。なくしてしまわない限りはね。もし破れたページをなくしてしまったとしても、他のページは全部読める。だから、ちょっと破けたくらいで紙の本の価値はあまり損なわれない。
・ずっと本棚に入れておくと陽射しで灼けたり、埃が積もる
→ちょっとクシャミを我慢すれば、その程度の経年劣化は問題にならない。今どきの本は中性紙だし、少なくとも自分が生きている間に読めないほど劣化してしまうことはないだろうし。
・汚れる、傷む、燃える
→火事にあったら、それはまずアウト。床上浸水で泥だらけになったら、アウトのケースもあれば、復活できるケースもあるかな。
ちょっと前から流行っているデジタル・アーカイブ。電子化すれば、文化財級の書籍もずっと後の世に残すことが出来る。彫刻や美術品もそうだ。でも、電子データの永続性を証明できた人はいない(と思うんだ)。
コンピューターはどんどん形を変えるし、読めなくなる昔のデータは増える一方だ。
そうではない、どんどん変化しても問題のない汎用的な形式にすればいい?
それも、まやかしに近いのではないかと、僕は思う。汎用的なデータは固有の機能を保ち難い。電子書籍だって、ePub形式が素晴らしいのは、現在のWEBの技術と極めて近しい構造だからではないかと思う。柔軟で、汎用的で。
でも汎用的なフォーマットにすることで、捨てざるを得ない機能はたくさんある。
だから、例えば昔の書籍をそのままの状態で全て保存したいと考えたなら、採用する形式はePubではない。形、色、質感も含めて保存するなら、きっとスキャン画像を元に立体化したCGデータになるのだろう。とんでもなく重いデータになるし、そもそも完全に復刻可能なデータなんて作ることは不可能だ。今のところ、臭いや触りごこちまで含めて完全な書籍そのものの情報をデジタルデータに閉じこめることは不可能だからね。CGの専門家が言うんだから、間違いない。(ということにさせておいて欲しいな。ここでは)
何とかそれなりに深い書籍情報をデジタルに閉じこめたとして、そんなデータが百年後の世界で通用すると思う?
きっと、元にした現物が残っている間に、デジタル・アーカイブのデータは使い物にならなくなるだろう。そのデータが使い続けられるように、技術革新を続ければいいのだと考えるかもしれない。でも、そうすると過去の古びた資産を切り捨てることが出来なくて、とんでもなく冗長なシステムが積み上がっていくことになる。今後もHTMLやCSSのバージョンはどんどん上がっていくだろうし、下位互換はある程度保たれるだろう。でも、ずっと下位互換を保つということはない。
例えばHTML1.0で作られたデータをモダンなブラウザで表示すると、やっぱり当時とは見栄えが変わっているはずだ。変わらないものもあるだろうけど、当時の技術をぎりぎりまで使い倒して作ったデータなんかは、どうしようもない。
現在、既にテーブルをレイアウトに使うことは非推奨とされているし、当時あれほどもてはやされた、テーブル・レイアウトでデザインされたページは、崩れてしまうことがある。やがては、ぐちゃぐちゃにしか表示されない時代も来るだろう。
少々ずれ始めたかな。
そろそろ、結論めいたものを書いておきたい。
(僕には何も決められないし、そもそも判断すら出来ないのだけど。それを前提に、個人的な、私的な意見として、ごく簡潔にまとめてみたい)
・電子書籍は便利だけど、まだ紙の本には全然かなわない。
・電子書籍のメリットがデメリットに勝つケースでは、活用が進む。これまでのように。
・将来的にも電子書籍が紙の本を駆逐するとは考えられない。少なくとも僕らが生きている間には。
・電子データだって、紙の本だって、永遠に保管なんてできない。それは複製されて、内容が残されていく。固定されたものとしてではなく、コンテンツという情報がかたちを変えて残されていくのだろう。
だから、電子書籍と紙とはどちらが優れていて、どちらが残るという議論は不毛なんだろう。
(そんな結論、何年も前からとっくに出ていたよ、って言わないで。僕は自分の考えをまとめたかっただけなんだ)
僕はこの先もKindleを持ち歩くだろう。じっくり家で読みたいものは紙の本でも読むし、その場で買いたい方を買うだろう。書店に行って本を見るのも好きだし、松丸本舗がなくなったときはとても寂しかった。
セルフ作家の本は電子書籍じゃなきゃ読めないケースが大半だし、Kindleがなかったら、僕はきっと小説を世に出すことが出来なかっただろう。
それがなくても、書くことだけはあっただろうと思う。とても若い頃から、僕はきっと本を書くという予感がずっとあった。でも、機が熟していなかった。僕はバリバリの作家志望ではないけど、電子書籍が出るずーっと前からちょこちょこと文章は書いていた。でも、本を書いたとしても、それが出版社に認められて世に出るかと言うと、それは決してなかったはずだ。
処女作がいきなり認められるような突出した才能はない。何冊も書いてきて、だんだん人に読んでと言えるようなものが書けるようになったんだから。
電子書籍には感謝している。好きだ。でも紙の本も同じように好きだ。
それでいいじゃないか。
まだまだダメな電子書籍だけど、ずっと付き合って行こう。
縁あってこれを読んでくださったあなたは、きっと電子書籍を読んだことのあるひとなのだと思うから、あなたもずっと、付き合ってくださいね。
(電子書籍に触れたことのないひと、スマホやタブレットで、一度も本を読んだことのないひとも、たくさんいるんだよなあ。e-Ink端末以外は目がとても疲れるから、あまり勧められないんだけどね)
さて、この記事が、いつか誰かの役に立ちますように!
← その−3へ