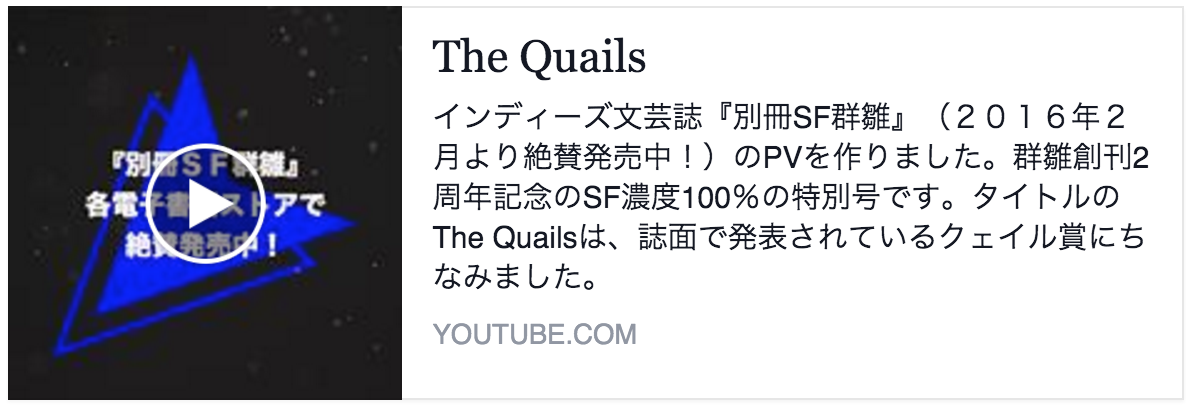いつか、
すべてを諦めてしまう日が
来てしまうのだろうか
当たり前に
何も作らずに
何も生み出さずに
日々を過ごすだけで
満足できる日が
来てしまうのだろうか
じゃあ、お先にって
誰にも言うことができず
この世界から
抜け出すことも出来ず
結局、
ずぶずぶと沈んでいって
もう、
浮き上がろうともせず
あちこちに
溜まりに溜まった
燃えかすを
振り返ろうともせず
もう一度
燃やそうなんて欲は決して持たず
君の笑顔だけで充分だと
そう
心から信じられる日が
来るのだろうか
でも、
でももし
そうなったら、
色んな場所に行こうか
君の行きたい場所に、
一緒に行きたかった場所に
色んなことをしようか
僕のために諦めてきたことを
きみがずっと
諦めてきたことを
今度こそ
一緒にしようか
僕が勝手に描いていた未来図は
君がいてこその
ものだったんだから